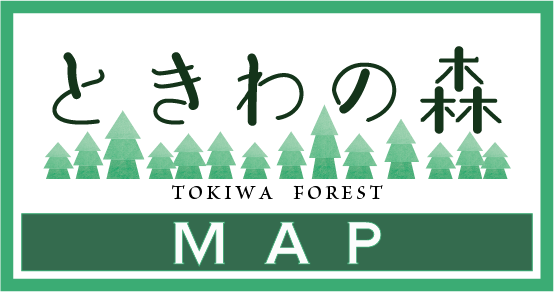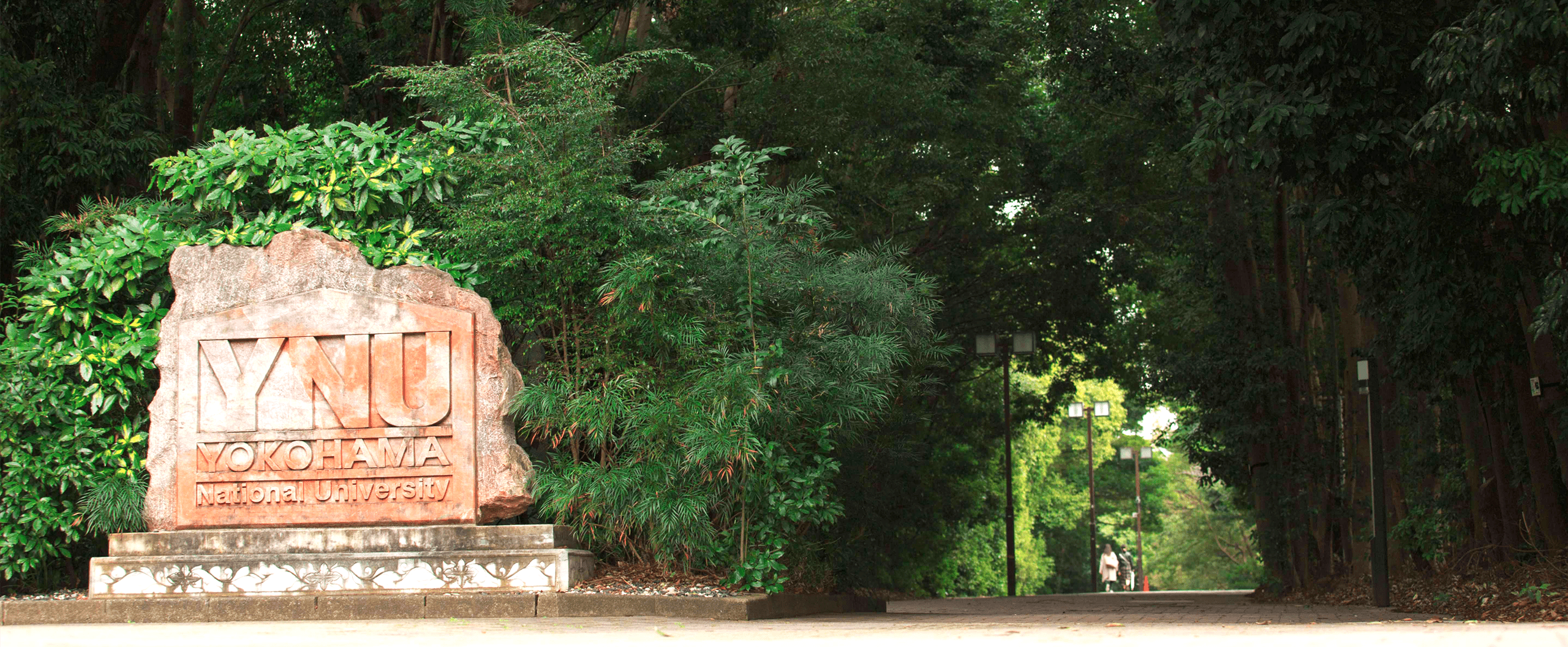
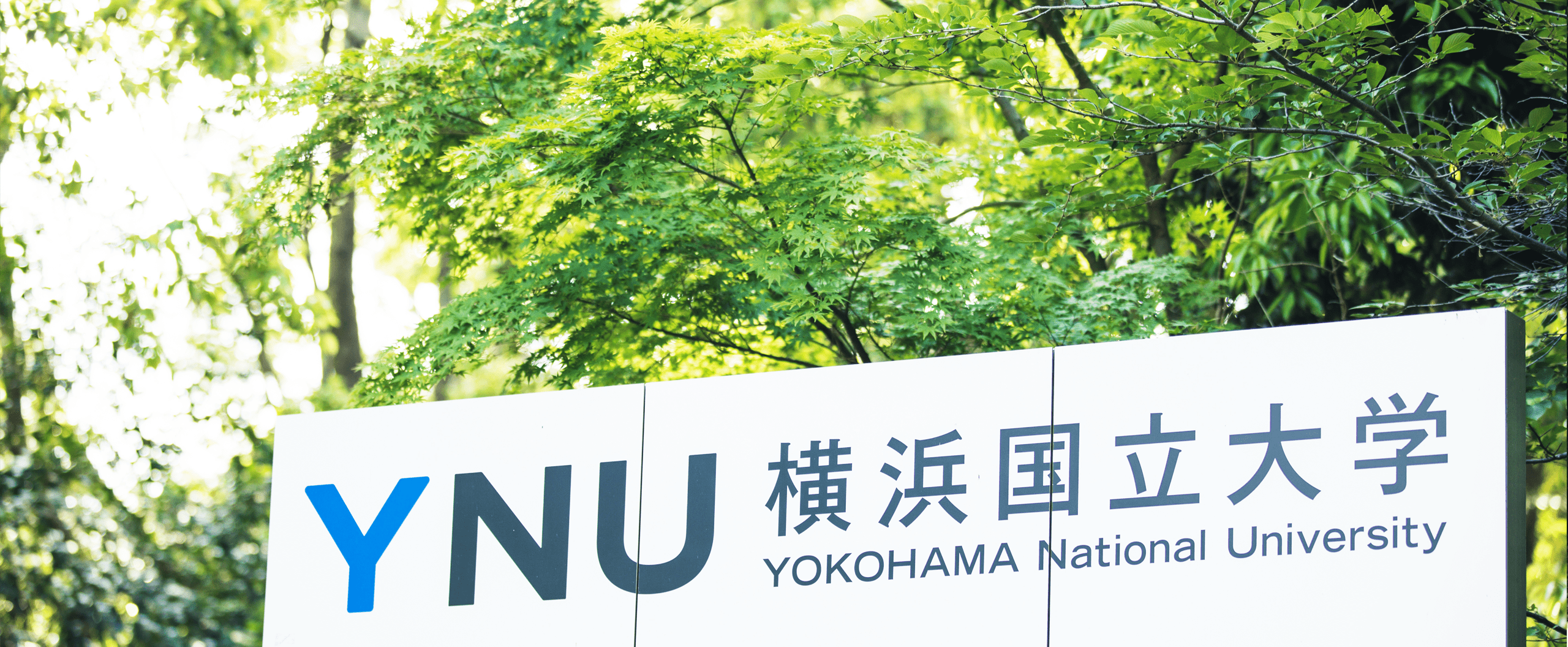

こちらは、「ときわの森めぐり」を
楽しくする小さな情報サイトです
★

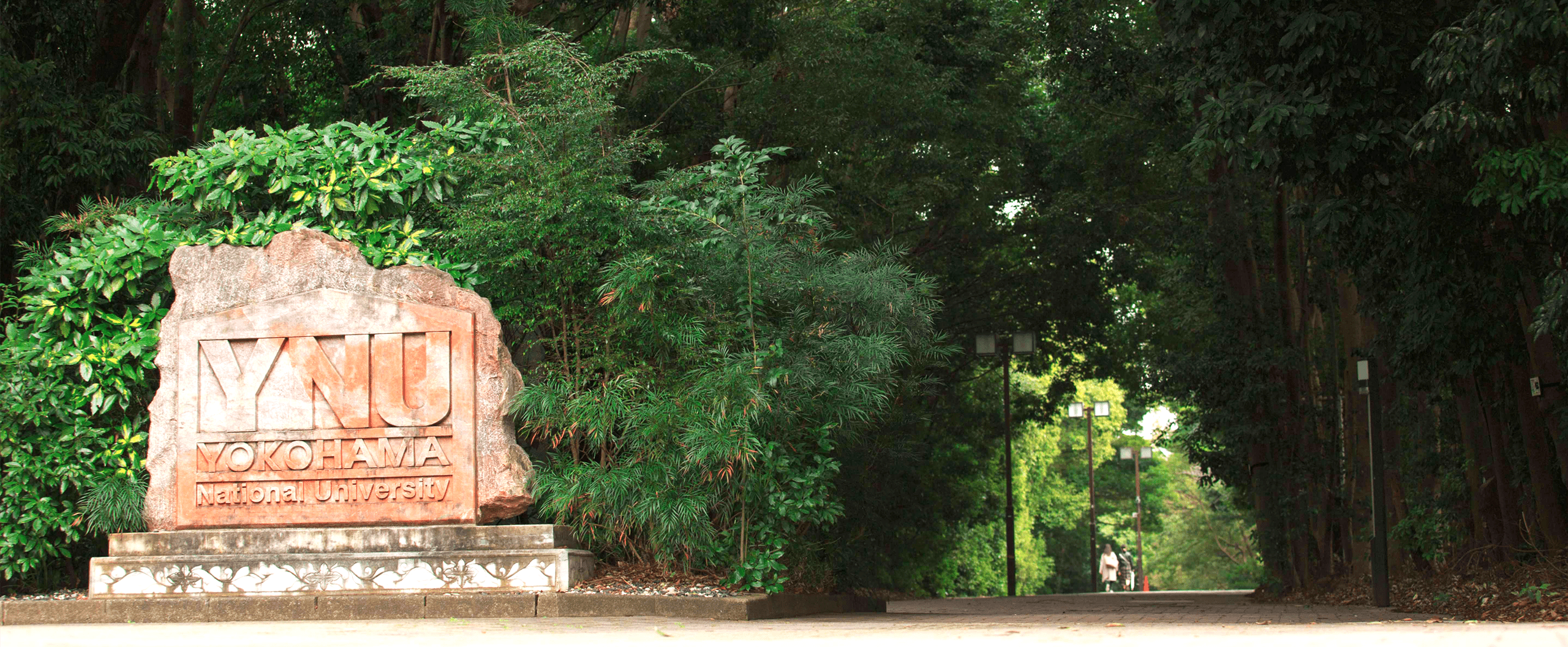
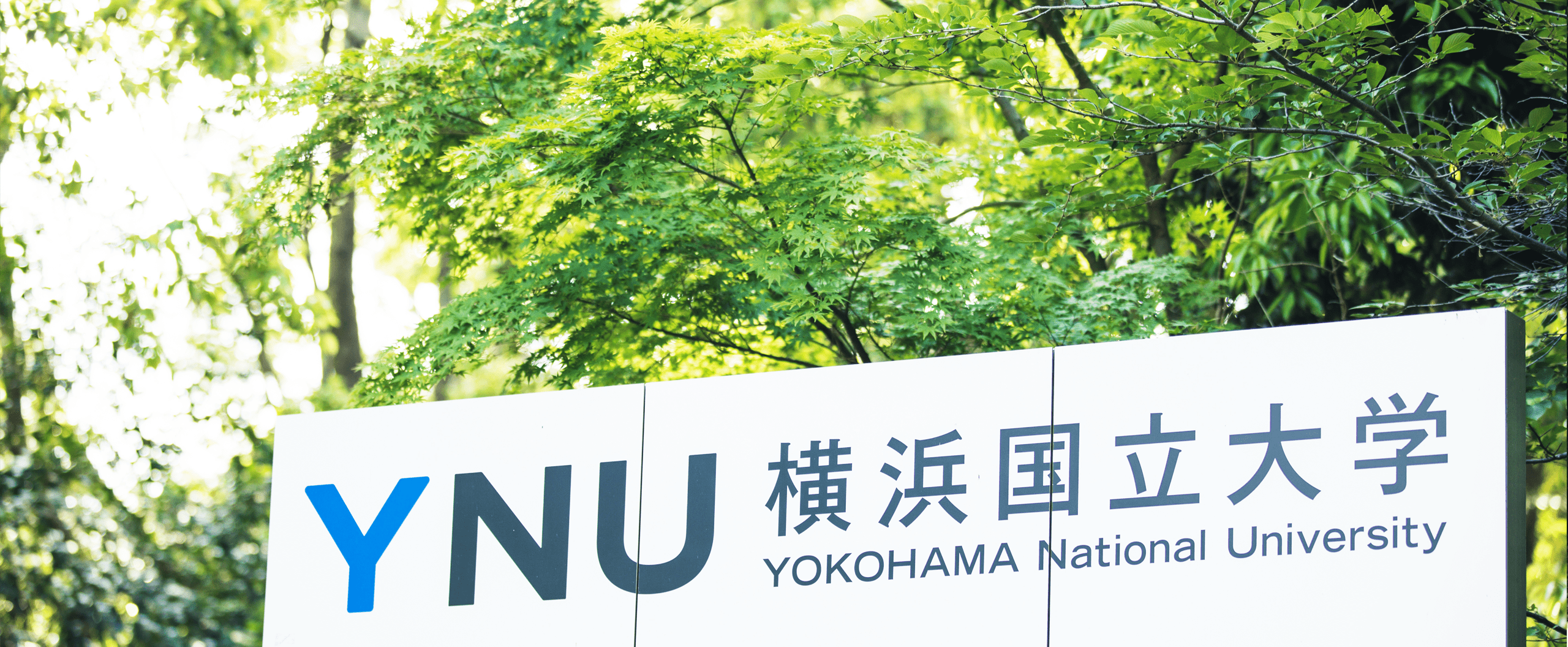

横浜国立大学の目玉となる自然や文化について,20~30分ほどで回れる散歩コースを設定しました。学内4か所のポイントに置かれたQRコードから,その場所の自然や文化についての解説を読むことができます。ぜひお散歩がてら,横浜国立大学をお楽しみください。

横浜国立大学キャンパスには,横浜の都市部とは思えないような豊かな森が広がっています。もともとゴルフ場だった敷地に大学が移転してきたのが1970年代後半,それから50年近くが経過し,今の景観をつくっています。 大学キャンパスには,多様な種類の森があります。ゴルフ場だった頃よりもずっと以前からあった天然の照葉樹林では,巨木となったスダジイやシラカシ,林床には希少なランが生育しています。また人が利用して管理されていたと思われる雑木林では,多くの樹種がみられます。
横浜国立大学を緑地創成の観点から有名にしたのは,故・宮脇昭名誉教授です。氏は「ふるさとの木によるふるさとの森づくり」をコンセプトに,神奈川の潜在植生でメンテナンスフリーな森を設計し,「高密度植栽方式」によって環境保全林を作り上げました。この方法は,たくさんの種類の苗木を高密度で植栽することにより,より早く潜在植生(極相林)に達することができる方式として世界的にも知られています。神奈川の潜在植生は照葉樹林ですので,今ではアラカシやシラカシ,タブノキを中心とした森になっています。これらの森は,気候を緩和したり,二酸化炭素を吸収したり,延焼防止の防火帯として機能したり,様々な役割を担っています。
一方で,適度な管理がなされた草地も生物多様性の観点からは重要です。年数回草刈りが行われる草地では,明るい環境が保たれています。また最近では,ヤギによる草地管理の実証研究もおこなわれており,低コストで持続可能な管理を目指しています。こうした明るい草地では,クサボケやワレモコウ,カントウタンポポなど,里山植物といわれる草本も多くみられます。
多様な植生は,多くの動物の生活も維持しています。エナガやコゲラ,カワセミ,モンミスジやクロマルハナバチなど,都市部には珍しい鳥や虫も多く生息する一方,近年ではクリハラリスやハクビシンなどの外来種も多くみられるようになりました。本キャンパスは外来種対策や木の落枝倒木など,緑地管理上のさまざまな課題も持ち合わせています。
環境省では,保護地域以外で生物多様性保全に資する地域を「自然共生サイト(OECM:Other Effective area based Conservation Measures)」として2023年から登録を開始しました。古くからの森や管理された草地,学生や近隣住民の人々が利用する場,さらには縄文時代に人が生活していた痕跡など,現在の横浜国立大学のキャンパスには自然と人が共生してきた歴史が息づいています。現在,自然共生サイトへの登録を目指し,調査を進めています。